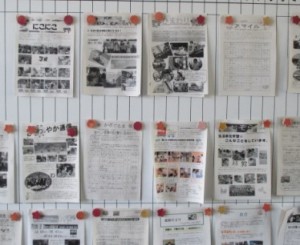昨日、A中学部陶芸班に発注していたマグネットが届きました。以前のものは、陶芸の部分が大きく、重たいために掲示物の枚数が増えるとずり落ちてしまうことがあったのですが、今回はその点が改良されて軽量でなおかつ使いやすいものになっていました。製品つくりでは、お客様の声が大切にされますが、働くことを学ぶ作業学習においても同じことが言えるのではないかと思っています。校長室には各学部の通信などがマグネットでとめて掲示してあるのですが、早速すべてA中学部のものに 取り換えました。
カテゴリーアーカイブ: 校長室
続けること・やりとげること
七夕
くすのき
本校は周囲を山に囲まれ、自然豊かな丘陵地帯(せいびの丘)にあります。たくさんの草木が見せる四季折々の姿は、季節感あふれるものです。そのたくさんの草木、特に樹木ですが、もともとあるものと後に植えたものとがあります。ソメイヨシノやベニカナメ、様々な果樹は後に植えたものです。一方もともとある樹木として特筆すべきは、校門のそばにあるくすのきです。樹齢は不明ですが、開校当時より西備の歴史をずっと見守り続けています。これから暑い時期に入るのですが、このくすのきが作る木陰が、ちょうど学校前のバス停を覆い、路線バスを利用する子どもたちを夏の強い日差しから守ってくれています。「大地に育つ」という言葉が本校にはありますが、このくすのきはそれを体現しているようです。
小さなことから
朝、校内を回っていると、教室のごみを回収場所まで運んでいく子どもたちの姿を見かけます。各学級で係活動として行っているものです。小学部の子どもであれば、少し大きなゴミ箱なのですが、しっかりと持って運んでいます。回収用のペールのふたを開け、ゴミを移し、ふたを閉め、教室に戻る。この一連の動きをどの子どもたちも一人で行っています。私たちは、将来、仕事や役割を通して社会に貢献する人を育てようと思っています。そのためにも、それぞれの学部や学年で、任された役割等を自分のものとしてしっかりと果たすということを大切にし、また育てていこうとしています。「小さなことからコツコツと」という言葉がありますが、今朝のごみを運んでいる子どもたちの姿を見て、改めてその意味を実感した次第です。 

共に 友に
今日、本校A部門・B部門中学部と神島外中学校との交流及び共同学習が、神島外中学校を会場に行われました。この学習は平成5年度から始まっており、今年度で23回を数えるものです。学習の内容は、その時代その時代で違っていますが、一貫して本校の生徒と神島外中学校の生徒が協力して何かをするスタイルとなっています。今年度は、ボウリングゲームと積み上げた段ボール箱の高さを競うボックスゲームでした。上級生になるほど早くから打ち解けて一緒に活動していました。一緒に楽しそうに活動する姿を見ると「共生」という言葉が絵になって目の前に現れました。色々な準備をしてくださいました神島外中学校の生徒のみなさんありがとうございました。
6月の掲示板
西備の竹箸
水曜を除く毎朝、9時30分ごろになるとラジオ体操の音楽が聞こえてきます。校長室の窓から外を見ると、竹箸班の生徒と教師がラジオ体操をしています。体操が終わり、しばらくすると切断機の回る音と生徒たちの元気な掛け声が聞こえてきます。長さ数mの竹が切断され、竹箸班の作業学習が始まります。切断された竹は、なたを使って縦に割られ、荒削りの行程に入ります。荒削り、中削り、仕上げ削り、そして先削り、これらの行程は機械を使って行われます。担当の生徒は、安全に留意し、真剣な表情で取り組んでいます。危険防止のため床面の清掃も欠かせません。できあがった箸は最後にサンドペーパーで磨かれ、一定の基準を満たしたものが西備の竹箸として製品になります。最近は外国から安い箸が大量に入っており、価格競争はできないのですが、西備の竹箸は、一膳一膳丁寧に作られていることは間違いありません。作業の最後には道具類の整理整頓と清掃をしてまた次の日の作業学習を迎えます。
.jpg)